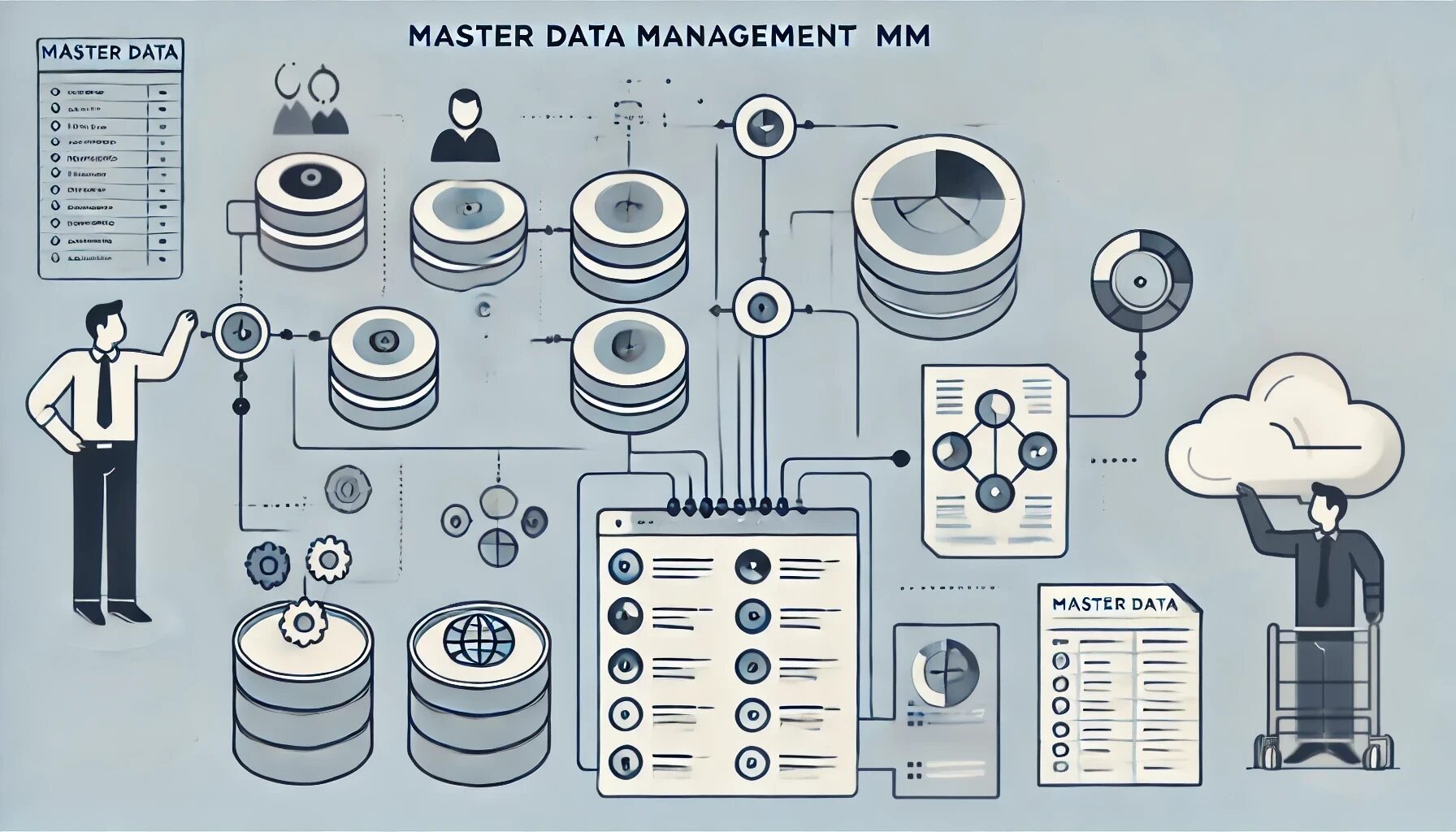システムの開発や刷新、導入を行う企業の担当者や、DX推進に取り組むリーダーが直面しがちな課題は、膨大なマスタデータの統合と管理です。
「コンサル企業を頼ればなんとかなる」と考える方も多いかもしれませんが、実際には事前に自社固有の業務ルールを反映状態としておかないと、期待した成果が得られない可能性が高いです。
「コンサル企業を頼るべきではない」ということではありません。
約800店舗を持つ小売企業で5年間システム刷新に携わった経験から得た結論は、「社内の業務メンバーによるマスタの事前整理こそが、最終的な工期短縮とコスト削減、現場の使いやすさに直結する」という点です。
本記事では、マスタ整備の全体像を一言でいうと「MDM(マスタデータ管理)を成功させるために、鳥瞰図と詳細図を使って社内にある情報を可視化する」ことをおすすめしていきます。
読者にとってのメリットは、要件定義やデータ品質向上のスピードアップ、そして追加的な手戻り防止です。
自分たちの業務を視覚化・定義をした後に、外部コンサルやシステム開発企業と連携すれば、DXで大きな成果を得られる可能性を高めることができることをお伝えします。
MDM(マスタデータ管理)を外注する利点と自社内作業の必要性
外注のメリット:豊富なノウハウと事例が提供される
専門コンサルやシステム開発企業に依頼するメリットは「多様な成功・失敗事例をもとに最適な解決策を素早く提示できる」点です。
実際、複数企業の事例や業界標準のベストプラクティスを知っているコンサルは、問題発生時の対処方法を体系的にアドバイスします。
さらに、要件定義から設計・開発まで一気通貫で対応できる企業を選べば、短期間でシステム構築に着手しやすいです。
一方で、自社特有のルールや業務ノウハウを正確に反映するには、自社メンバーによる情報整理が欠かせません。
外部企業だけに任せると、属人的な運用や特殊ルールが十分に伝わらず、後から「本当はこの情報が必要だった」という追加要件が出てくる危険性があります。
これにより、開発のやり直しやコスト増につながる可能性が高まります。
自社でのマスタ項目整理を怠ると起こり得る失敗
自社でのマスタ項目整理をしないまま開発に着手すると、次のような失敗が発生しやすくなります。
- コンサル企業が提示した標準マスタに合わないデータが多数発生し、手直しが相次ぐ
- 開発終盤で「一部の店舗で仕入先が異なる」「特定カテゴリーだけ別規則がある」など未把握の要件が判明し、再設計が必要になる
- 結果的に工期や予算が大幅に超過し、プロジェクト全体のマネジメントが混乱
上記のような状況になってしまうと、管理職や経営層からのプロジェクト評価が下がるだけでなく、せっかくのDX推進やシステム刷新が「自社への不必要な負担」と捉えられかねません。
重要な要件が漏れていて必要な情報は不足していると最終的には現場がシステムの利用を敬遠し、導入の意味が薄れる危険性もあります。
したがって、事前のマスタ項目整理はプロジェクトの根幹を支える工程であり、これを怠ることは極めてリスクが高いことと認識することが重要です。
マスタモデル図の役割:全体俯瞰と詳細把握で漏れ重複を防ぐ
鳥瞰図がもたらす効果:管理対象を明確化し、重複や欠落を防ぐ
マスタ関連図を作成する際、最初に取り組むのが「鳥瞰図(全体モデル図)」の作成です。
これは「商品」「店舗」「物流センター」「仕入先」など、管理対象となる大きなくくりを図上に並べ、相互の関係を線や矢印で示す手法です。
2.png)
鳥瞰図が重要な理由は、「全体像を一目で理解でき、管理する対象の重複や漏れを早期に発見できる」ことです。
もし鳥瞰図を作らずに個別システム開発へ突入すると、「仕入先情報は別システムでも扱っていた」ことに後から気づき、データの不一致や二重管理によるミスが増えます。
このような事態は、後戻りで多大なコストを生み、プロジェクトを停滞させる大きな要因です。
実際に約800店舗を抱える小売企業での全社システム刷新プロジェクトでも、初期段階で社内外の関連システムを洗い出し、鳥瞰図を作りました。
結果として、重複して管理されていた商品情報や店舗情報が判明し、データ統合を効率よく行えました。
「鳥瞰図が全てのマスタの起点になる」と言っても過言ではありません。
詳細図がもたらす効果:要件定義と追加コスト削減
次のステップは、管理対象ごとの「詳細図」を作成することです。
詳細図では、各管理対象(例:商品マスタ、店舗マスタなど)が保持する具体的なデータ項目をすべて洗い出し、相互のつながりも含めて細かく記載します。
-1.png)
例えば「商品」に以下の情報があるとします。
- 商品名
- 仕入先
- 原価
- 売価
ところが、店舗ごとに仕入先や売価が異なる場合、商品マスタとは別に「店舗別商品マスタ」を作り、そこへ店舗に応じた情報を持たせる必要があります。
この分割設計を行わず、ひとつのテーブルに詰め込んでしまうと、データ量や管理ルールが増加して複雑化します。
一方で、不要に細分化しすぎるとシステムの結合が煩雑になり、利用時に混乱が生じる可能性があります。
詳細図を作りながら必要に応じて「どこまで同じ管理対象に含めるか」「どの情報を別管理対象に切り出すか」を検討すると、要件定義時に明確な根拠をもってシステムベンダーに指示できます。
この段階で検討を怠ると、開発後に「別管理対象にすべきだった」「結合関係が適切でない」といった再設計が必要になり、追加コストが発生します。
したがって、詳細図の作成は開発費の最適化にも直結します。
管理対象を分割する具体例:店舗別商品
店舗別の仕入先や売価が引き起こす問題
商品マスタがある程度整備されても、店舗ごとに仕入先が異なる場合、単純に同じ「仕入先」項目を使えないケースがあります。
A店舗とB店舗で扱う商品は同じでも、仕入先が違えば当然、原価や売価も異なる可能性が高いです。
こうした店舗別の差異を商品マスタだけで扱うと、以下のような問題が発生します。
- 商品マスタのレコード数が膨大になり、管理が煩雑になる
- 同一商品でも店舗が違えば別レコードとして扱う必要があるため、重複データが増加する
- データ登録や更新作業が増え、入力ミスや不整合が起きやすい
このような状況が続くと、店舗ごとの在庫管理や売上分析で参照すべきデータが不安定になり、経営判断にも影響が出ます。
そこで、店舗別商品を独立した管理対象(マスタ)として切り出し、店舗ごとの情報を明示的に管理する設計が推奨されます。
別管理対象(マスタ)で管理した場合のメリット
鳥瞰図や詳細図をもとに「商品マスタ」と「店舗別商品マスタ」を分割すると、以下のようなメリットが得られます。
- データ重複の抑制
商品そのものに共通する情報(商品名、基本原価など)は商品マスタに持たせる一方、店舗ごとの差異(仕入先、店舗別売価など)は店舗別商品マスタへ切り出すことで重複管理を減らせます。 - 更新作業の明確化
店舗別情報を更新する際は「店舗別商品マスタ」だけに対して変更を行えばよいため、運用担当者の作業範囲が分かりやすくなります。 - 将来的な拡張が容易
新店舗が増えたときは、店舗別商品マスタにレコードを追加するだけで済み、商品マスタの構造変更は不要。
その結果、システム全体を大きく再設計するリスクが低減します。
このように別管理対象(マスタ)で管理することで、データの整合性が保ちやすくなり、長期的な運用コストを削減できます。
項目定義書の重要性:運用時の混乱を防ぐ鍵
項目定義書を作る理由:データの意味と使い方を明示する
マスタ関連図を作るだけでは「なぜこの項目が必要なのか」「どの部署がいつ更新するか」など、具体的な運用ルールが曖昧になりがちです。
そこで必須なのが、項目定義書の作成です。
項目定義書は、「項目名」「データ型」「用途」「更新頻度」「入力フォーマット」「管理担当部署」などを記載し、全員が共通認識を持てるようにします。
項目定義書がない状態で運用を始めると、実際の運用担当者が「この項目の値はいつ変更していいのか」「推定で入力してよいのか」など、判断に迷うケースが多発します。
結果的にデータがバラバラに更新され、最終的には正しいデータがどれなのかわからない事態になりかねません。
このリスクを回避するためにも、項目定義書による統一ルールの周知は必須です。
項目定義書がもたらす長期的メリット
項目定義書を整備すると、将来的にシステム連携やバージョンアップを行う際にも混乱を最小限に抑えられます。
たとえば新しい在庫管理システムを導入するときも、「既存のマスタにはどんな項目があるか」「どのように連携すべきか」をすぐに把握できます。
その結果、プロジェクトスケジュールを組みやすくなり、後工程で修正が頻発するリスクも減少します。
また、データガバナンスの面でも有用です。
担当者が変わっても、定義書の存在によって必要なルールが引き継がれやすく、担当者交代による混乱も防げます。
すなわち、項目定義書は「運用やメンテナンスの指針」として長期的に機能し、DX推進の足場を安定させる効果があります。
DX推進とマスタ整備の関係:データ活用を成功に導く鍵
なぜDX推進は正確なマスタが前提となるのか
DX(デジタルトランスフォーメーション)を実現するには、多種多様なデータを統合的に分析し、意思決定に反映させる必要があります。
マスタが整備されていない状態でBIツールやAI解析を導入しても、商品名の表記ゆれや売価の不一致などが発生して、分析結果を歪める危険があります。
つまり「誤ったデータからは正しいインサイトは得られない」という当たり前の事実が、DX推進において致命的な障害となるのです。
逆にいえば「マスタ整備が完了している企業は、DXの取り組みで確かな成果を得やすい」とも言えます。
商品マスタや顧客マスタが正確かつ更新ルールが明確であれば、あらゆる分析や新施策のテストも迅速に行えます。
この点からも、マスタ整備がDXの土台を支える重要な工程であることが分かります。
自社でのマスタ整備がもたらす運用コスト削減
DXの取り組みが進むと、新たなシステム連携やデータ活用の場面が次々と生まれます。
たとえばECサイトと店舗在庫のリアルタイム連携、AI需要予測システムへのデータ供給など、多岐にわたる接続が発生します。
こうした接続が増えるほど、マスタの正確性と更新ルールの明確化が重要になります。
自社でマスタ整備のプロセスをしっかり経験しておくと、どのようにデータを管理すべきか理解が深まります。
外部ベンダーやコンサルに再度依頼する際も、要件や期待成果を的確に伝えられるため、不要なミスや手戻りを減らし、結果的に運用コストを抑制できるのです。
まとめ
MDM(マスタデータ管理)導入を円滑に進めるためには、自社でマスタモデル図(鳥瞰図と詳細図)を整備し、項目定義書を作成して外部コンサルと連携をしていくことを推奨します。
自社の業務ルールや店舗特性を最も理解しているのは現場担当者だからです。
外部コンサルには幅広い事例やノウハウがある一方、企業固有の細かな要件やルールは伝わりにくく、追加設計や手戻りを招くリスクがあります。
マスタ整備を事前に行えば、要件定義が明確化し、開発期間短縮と追加コスト削減が期待できます。
私が参加したプロジェクトでは、初期段階でマスタ再構築と定義書の整備しました。
その結果、後続のシステム開発フェーズで情報が円滑に伝達できたことで、必要以上の確認や手戻りが発生しない状態となりました。
もし初期段階の整理を怠っていたら、店舗別の仕入先や価格設定などが後から判明し、再設計やシステム修正が頻発していたはずです。
まずは自社内で鳥瞰図を作り、管理対象の全体像を把握しましょう。
次に詳細図で各項目を洗い出し、項目定義書に更新ルールや運用責任者を明記します。
これを基にコンサルやシステムベンダーと協議すれば、スムーズな要件定義が可能になり、DX推進においても高い効果を得られます。
マスタ関連図の作成方法を参考に整理をぜひ進めて見てください。